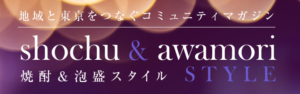【蔵元インタビュー】宇都酒造・鹿児島県 / 焼酎杜氏発祥の地で生まれ育った使命。「杜氏」として”飛びっきり旨い酒”を届けたい――宇都尋智さん
「杜氏」という職業にひときわこだわりを持つ、一人の蔵元がいます。宇都酒造株式会社 宇都尋智さん。彼が追い求めるのは“旨い酒”ではなく“飛びっきり旨い酒”。そこには焼酎杜氏発祥の地・南さつま市に生まれ育ったからこそ湧き立つ想い、「杜氏」という職にこだわる姿勢があります。3年前の春に発売された芋焼酎「金峰 紅」は、宇都さんが飛躍するきっかけとなった銘柄です。自蔵に戻って15年目、杜氏として10年目。節目の今年、まだまだ進化の力を秘めた宇都酒造の現在と未来を語っていただきました。宇都酒造「金峰 紅」ファンの方も、まだご存じではない方も、杜氏発祥の地で挑戦するひとりの蔵元の姿をご覧ください。
【profile】 宇都 尋智 / Hirotomo Uto
1978年生まれ。鹿児島県南さつま市出身。宇都酒造株式会社 代表取締役社長 兼 杜氏。2001年に東京農業大学 応用微生物学科卒業。大学卒業後の3年間、和歌山県の清酒蔵で修業を経て、2004年より宇都酒造株式会社4代目として自蔵に戻る。2008年より杜氏を兼ね、2016年12月社長に着任。現在は杜氏として蔵の生産責任者を担いながら、経営部分をハンドリングしている。
宇都酒造株式会社
1903年(明治36年)創業。代表銘柄「天文館」「金峰」「金峰 紅」。鹿児島県南さつま市加世田にある酒造蔵。南さつま市は鹿児島県における2大杜氏集団発祥の地でもあり、笠沙という地域に黒瀬杜氏、金峰という地域に阿多杜氏がそれぞれ拠点としていた。全国の焼酎蔵では、宇都酒造のように黒瀬杜氏や阿多杜氏を招かずに自蔵で杜氏を育成し伝統継承する「地杜氏」(じとうじ)も多い。
〒897-1125 鹿児島県南さつま市加世田益山2431
[アクセス]鹿児島空港から高速バスで加世田バスステーション下車後、タクシーで5分 または 鹿児島空港から車で60分
社長として蔵をハンドリングする立場に。周りの理解を得るために意識したこと

(yukiko)ここ数年で焼酎業界の取り組みもさらに活発になってきましたが、宇都さんのなかで変化はありましたか?
(宇都さん)2016年12月から社長に着任したことは大きいですね。責任も大きくなっているけれども、父からバトンを正式に受け継いだことによって、経営者として迷いがなくなってきました。例えば、原料発注など資金データなどを具体的に見るようになりましたし、きちんと売り上げを確保したり、宇都酒造の方向性を定めるうえで何が必要なのか、何をやるべきなのか立場上明確になりました。それによって自分の行動も明確になったと感じています。
(yukiko)宇都さんが2004年に蔵に戻ってきて「杜氏」になった時のエピソードがあれば教えて下さい。
(宇都さん)2008年の杜氏になりたての頃、”旨い酒”を造りたいために試行錯誤しました。その分、昔からうちの蔵で働いてくれていた人たちに、新しいことや変化を受け入れてもらうまでは苦労した経験があります。どの仕事にも言えることだと思いますが、今まで慣れたやり方や仕事の仕方を変えるのは勇気や覚悟がいることです。”旨い酒”を造るために模索し、様々な方法を試す自分自身を理解してもらうために、実際に飲んでもらったり工夫をして、周りの理解を得てきました。
実際に、自分が”旨い”と思った焼酎を全国の方に飲んでいただいた時、「今までよりも美味しい酒になった」と評価してもらえるようになったんです。それによって蔵人の理解も深まりましたし、さらに自分が蔵の方向性を最終決定する社長という立場なったことで、蔵人が私の意見に対してスムーズに耳を傾けてくれるようになりました。
(yukiko)酒造りという”仕事”がしやすくなったのですね。
(宇都さん)そうです。例えば、利き酒をして原因追究をした後も、蔵の人たちと情報共有がきちんとできた状態で製造に向かえるようになりました。そのため、こちらが細かく指示を出したり、目を配っておく必要がなくなり、言わなくても理解してもらえる環境になりました。
(yukiko)「社長」という立場になったことで、宇都さんが意識していることはありますか?
(宇都さん)「肩書きだけでは、人はついてこない」と思っています。自分に初めて「杜氏」という肩書きがついた頃、先ほどお話したように、なかなか自分が求める変化についてきてもらえなかった。最初はこちらの指示したように動いてくれていても、すぐに慣れていた元のやり方に戻ってしまったり……。
従来の方法で満足している意識や環境が浸透していたり、自分自身が「杜氏」として認めてもらえていなかった部分もあったのだと思います。だからこそ、これからきちんと行動で示したいですし、「杜氏」という技術者としての経験を積んでいきたいと思っています。
「杜氏」としてこだわりたい――途絶えゆく、焼酎文化を支えてきた杜氏集団へのリスペクト
(yukiko)宇都さんはいつ頃から杜氏になりたいと思っていたのですか?
(宇都さん)幼い頃から杜氏の仕事を見ていて、まずは純粋に「かっこいいな」と思っていました。憧れの職業だったんです。学生時代から焼酎の製造部分に携わりたいと思っていました。杜氏になるために大学進学もしましたし、日本酒蔵で修行も積みました。
(yukiko)宇都さんは「社長」と言われるよりも「杜氏」として皆さんから認めてもらいたいと強く思っている方ですよね。宇都酒造のある南さつま市は、鹿児島の本格焼酎を語るうえで欠かせない杜氏発祥の地でもあります。そういう環境の影響もありますか?
(宇都さん)うちの蔵がある南さつま市は、黒瀬杜氏・阿多杜氏(あたとうじ)の“2大杜氏発祥の地”であって、それぞれの杜氏集団には独自の製造技術が伝承されていました。その姓を名乗る杜氏を九州内に多く輩出し、日本の焼酎文化を発展させてきた素晴らしい功績があります。
(yukiko)鹿児島では、この2つの杜氏集団以外は「地杜氏」(じとうじ)と呼ばれる、自蔵で杜氏を育成して技術を継承していくパターンですよね。読者の皆さんに分かりやすく説明するなら、宇都さんはこちらに属します。
(宇都さん)そうです。黒瀬杜氏・阿多杜氏を名乗るには多くの条件を満たしていないといけないので、私はそこには属せません。今では現役の黒瀬杜氏、阿多杜氏は後継者がいないため、焼酎業界を支えてきた一流の杜氏が生み出す技術を直接受け継ぐ人がいない現実があります。
私は南さつま市に住んでいるからこそ、ありがたいことに引退した杜氏の皆さんと年2回ほど一緒にお酒を飲む機会があります。毎年春になるとその年にできた新酒を持っていって、黒瀬杜氏・阿多杜氏として活躍していた方々に色々なことを教えてもらっています。
そのなかで自分が蔵で培った技術を裏づける話や、聞いたことのない造りの方法を聞くことができます。私は黒瀬杜氏・阿多杜氏の姓を名乗ることはできませんが、南さつま市に生まれ育ったからこそ、その方々の想いや技術を受け継いで自分なりの表現をしていきたいと思っているんです。
杜氏になって今年で10年目。黒瀬杜氏・阿多杜氏のなかで昔から伝えられている知識を吸収し、それを活用する知恵を受け継いでいくことも、南さつま市に蔵を構える「宇都酒造 杜氏」としての“使命”なのもしれません。
(yukiko)では、それを踏まえたうえで……今後、宇都さんはどのような杜氏になることを目指していますか?
(宇都さん)昔の杜氏は蔵と契約していて、数年ごとに所属する蔵を変えることが多かったようです。環境が変わってもその蔵や水設備に合わせた焼酎を生み出していました。これは長年培ってきた技術や知識、経験を総動員してより良いものを求めて造り続けていたからだと思います。
自分のなかで杜氏とは、焼酎の味の造り分けが出来るくらいの技術を持った職人であるべきだと考えています。結果論ではなく“意図した味わい”を生み、表現し続けてくことが大切なのだと思います。
クラフト感と現代的な味わいが表現できる杜氏・宇都尋智が醸す芋焼酎「金峰 紅」
(yukiko)発売してから着々とファンを増やしてきている銘柄が、紅芋を使用した「金峰 紅」ですよね。私は1年目から飲む機会があり、焼酎のクラフトの部分は保ちつつも今までにありそうでなかった現代的で洗練された着地点が表現されている印象を受けました。
それは商品のラベルデザインにも顕著に表れていました。本格焼酎のなかでも珍しい赤を使用していて、きちんと酒質を表していた”モダンな赤”だったんです。世の中に無数に存在する赤のなかでも、この赤を選んで商品発売した蔵元の感性に驚きました。「金峰 紅」という新たなチャレンジがきっかけで、宇都さんの潜在的な感性が焼酎を通して表に出てきたな、と。このような銘柄を発売したきっかけを教えていただけますか。
(宇都さん)きっかけ的なことを言えば、「変わらないために変わる」……この言葉が大きいです。自分の人生において、とても大きな影響を受けている言葉です。「変わらない」とは大きな意味で宇都酒造という存在が続くことを指し、後半の「変わる」とは“酒質の進化”や“ブラッシュアップ”という意味合いが強いです。
宇都酒造の文化や受け継いできたもの、根幹的かつ大切な部分は残しながら”変化”を加え続けて行くことが自分の酒造りに対する姿勢でもあります。芋焼酎「金峰 紅」を世に送り出したのも、その一環だと言えます。

さつま芋品種・黄金千貫の芋切り作業。宇都酒造の本格焼酎は人の手によって丁寧に造られている
(yukiko)「文化」には受け継がれてきたものを変えずに“守る”場合もあるでしょうが、それだけではない側面を持っていますよね。
(宇都さん)例えば、芋焼酎が生まれた頃に使用されていた麹は、清酒で使われている黄麹で造られていました。現在、主流になっている白麹や黒麹ではなかったんです。もし変わらないことが大切であるならば、今も変わらず黄麹が主流のはずです。
芋焼酎の原料としてポピュラーなさつま芋品種・黄金千貫も、長い間、鹿児島で培われた優れた文化のひとつです。それを踏まえたうえで、3年前に黄金千貫とは違った酒質を持つ芋焼酎を試してみるのも良いのかなと思い、仕込みを始めました。最初の年はあくまで試醸として「紅さつま」「紅はるか」の2品種を試したんです。
(yukiko)実際にいかがでしたか?
(宇都さん)不思議なことに、両方とも果実のような芳香があり、白麹との相性も抜群で、「紅さつま」で仕込んだ焼酎はリンゴのような香り、「紅はるか」で仕込んだ焼酎は巨峰や梅の香りを持つ焼酎となりました。
傾向が最初の仕込みで見えたのちに、もう少し甘さをのせて軽快さを出すには……と考え、自分のなかにある技術を入れ込み、現在の「金峰 紅」が出来上がっています。芋焼酎「金峰 紅」は、前年のものよりもさらに洗練された味わいを目指しています。
(yukiko)宇都さんが「金峰 紅」に投じる、“洗練された味わい”とは?
(宇都さん)紅芋が持つ甘さやどっしり感というよりも、飲んだ時の感覚が爽やかでスタイリッシュなイメージを表現しています。
(yukiko)紅芋を使用する焼酎は、一般的に“甘さが感じられて飲みやすい”というイメージが持たれていますよね。実際に、市場ではそのような紅芋の銘柄も多く出ています。
(宇都さん)もちろん市場動向に寄せたマーケット・インも大事だけれども、私は技術者として自分が“すごい”と感じられるものを生み出していきたいんです。どちらかというとプロダクト・アウトの考え方に近いかもしれません。高品質で、自分の感性と技術を投じられて、なおかつ飲み手の人たちが笑顔になってもらえる本格焼酎を生み出していくのが理想なんです。
(yukiko)新たな時代や流行をつくってきたAppleやSONYもプロダクト・アウト型の企業です。革新的・先駆者的な企業は、たいていこのタイプに属しています。宇都さんもその感覚を持っている人。宇都酒造の銘柄のなかでも、特に「金峰 紅」はその傾向が顕著に表れている銘柄です。
焼酎スタイリストとしては、「焼酎&泡盛スタイル」読者の皆さんにも「杜氏 宇都尋智」という人物が生み出す本格焼酎を、そして「金峰 紅」という銘柄を、こういう観点で注目してみても面白いのではないかと思っています。
(宇都さん)もちろん伝統文化産業として、宇都酒造として後世へ受け継いでいくことも考えなければいけないことなので、双方のバランスを考えながら自分の技術表現を磨いていきたいですね。「金峰 紅」もまだ進化させられる感覚もありますし、“飛びっきり旨い酒”を飲み手の皆さんに届けたいと思っていますので、ぜひまだ「金峰 紅」を飲んだことのない皆さんにも飲んでいただきたいです。
「杜氏」として高みを目指す蔵元が考える、焼酎の楽しみ方

(yukiko)「焼酎&泡盛スタイル」は現代のライフスタイルに合った伝統文化産業「焼酎」を楽しんでもらう提案をしている媒体です。宇都さんが考える、この時代の”おしゃれな飲み方”とは何でしょうか?
(宇都さん)女性も男性もおしゃれにカッコよく飲みたいのは共通心理だと思っています。まずは、家でどのようなシチュエーションで楽しむのかを大事にしてほしいですね。単に“淡麗”とか“濃い”というのではなくて、どのように美味しいのかという“グレード“や”調和“を考えてみると良いのでは?
(yukiko)「杜氏」という職にこだわる宇都さんが飲み手に対して大事にしているポイントは何ですか?
(宇都さん)宇都酒造の焼酎は、なめらかさを大事にしています。蒸留酒独特のアルコール臭やピリピリ感を感じさせずに口のなかの感覚を大切に届けたいと思っています。そのため、芋焼酎「天文館」はすっきりしていて水割りやロック好きな方にもおすすめですし、「金峰」はお湯割りだと香りが立ちます。紅芋を使用した「金峰 紅」はロックや炭酸割りにする方も多いですね。
(yukiko)ちなみに男性読者に向けて、どのように焼酎を楽しんでほしいですか?
(宇都さん)これからの時期はキャンプやバーベキューが好きな人は焼酎を持って行ってほしいですね。お酒の弱い人・強い人によって割り方を変えられてアルコール度数を下げることができます。シーンを大事にして飲んでもらえたら嬉しいです。
自分の生き方をしっかり持って生活している男性って、自分から見ても格好良いと思いますし、リスペクトしたくなります。わいわいと賑やかに飲むのも良いけれど、シーンを大事にしたりひとつひとつ味わって飲んだりするお酒の楽しみ方もあります。紅芋を使った「金峰 紅」はすっきりとした飲み心地もあるので、女性だけではなくて男性にも楽しんでもらえる芋焼酎です。
(yukiko)宇都酒造「金峰 紅」は、ファッション誌や東京のイベントで紹介しても予想通り評価が高くて、女性ファンと同じくらい男性ファンも多いんです。日本のお酒として焼酎が持つクラフト感と、杜氏の現代的な感性が融合した芋焼酎「金峰 紅」は、ホテルのラウンジやバーでも似合う銘柄です。男性と女性が一緒に楽しめる銘柄ですし、男性からこの銘柄をおすすめされたら女性としても嬉しいですね!
ちなみに……宇都さんは日ごろ、どのように焼酎を召し上がっていますか?
(宇都さん)よく自宅で行っている飲み方として、1本は自社の銘柄・残り5本は他の銘柄を飲んでいます。自社銘柄だけだと慣れてしまうため、ほかの銘柄と飲み比べることによって頭のなかも味覚もリセットしています。あとは……他社の銘柄は外だと頼みづらいというのもあります(笑)。
(yukiko)他の蔵元の皆さんも、同じことをおっしゃいます(笑)。では、「金峰 紅」はどのような料理と合わせるのがおすすめですか?
(宇都さん)紅芋を使っていると“甘め”と思われる方もいるかもしれませんが、「金峰 紅」はリンゴのような爽やかな香りや品の良いカカオのような香りも持ってる芋焼酎なので、紅芋を使用していながらもすっきりしています。そのため、焼き鳥やピザにも合いますよ。
(yukiko)そうそう、タレやピューレを使用する料理に合いますよね!
(宇都さん)「金峰 紅」はロック、水割りも美味しいですし、飲食店では炭酸割りにするところも多いようです。紅芋なのにすっきり感があって爽やかなので、これからの行楽シーズンにも合うと思います。ぜひ試してほしいです!
宇都酒造が担っていく、今後の焼酎業界のポジションとは

(yukiko)宇都さんの今後のビジョンを教えて下さい。
(宇都さん)杜氏になって10年目。宇都酒造を牽引していく社長という立場になって、さらに将来にまで受け継がれる蔵でありたいと思うようになりました。そして、それ以上に「杜氏」という技術者にこだわっていきたいです。
私が育った南さつま市は笠沙地区に黒瀬杜氏、金峰地区に阿多杜氏が活動拠点にしている2大焼酎杜氏発祥の地。焼酎産業を支えた杜氏継承の形は時代の流れとともに変わってしまうかもしれませんが、この地で生まれ育ったからこそ、少しでもその精神や技術を受け継いでいきたい。南さつま市に蔵を構える宇都酒造の使命として、ここ数年で強く考えるようになってきました。自分なりに技術を磨いていきたいと思っています。
(yukiko)宇都さんの世代は、これからの焼酎業界をリードしていくゴールデンエイジ。そのなかでも「杜氏・宇都尋智」としての個性が際立っていってほしいですし、まだ宇都さんをご存知ではない皆さんにも注目してほしいですね。

(宇都さん)あくまでも、自分の肩書きは「杜氏」でありたいんです。それは、「杜氏」として自分をどこまで高められるかという挑戦の意味でもあります。決意表明というか……。焼酎造りにおいて原料の特性をどこまで出せるのか追究していきたいし、良い焼酎を造って付加価値を与えたい。“普通に旨い”ではなく、“飛びっきっり旨い酒”を造っていきたいんです。
ありがたいことに宇都酒造「金峰 紅」は都市部でも評価は高いし、地元でも高いんです。身近な人たちから「美味しかったよ」と電話をもらうこともあります。自分の友人知人にまずは褒めてもらいたい。そういうシーンに出会うと、とても嬉しいですね。

(yukiko)最後に、読者の皆さんにメッセージをいただけますか?
(宇都さん)最初に述べた通り、宇都酒造が50年後も100年後も焼酎を造り続けていくこと、そのための手段として、より旨い焼酎を生み出していく必要があると思っています。当面は、「杜氏」として自分が手掛けた焼酎に対して自分自身が感動して泣けるくらいの焼酎を造り、飲み手の皆さんにそれ以上の感動と笑顔を届けたいと考えています。
(yukiko)宇都さん、ありがとうございました。
特別編!蔵元と焼酎スタイリスト、それぞれのイメージは?
蔵元と焼酎スタイリストyukikoさんそれぞれに、お互いのイメージを聞いてみました。信頼しているからこそのコメント続出!?互いの個性がわかるコメントです。
■蔵元:宇都さん→「焼酎スタイリストyukiko」のイメージとは?
(宇都さん)「いつ睡眠を取っているのかな?」と思うほど、同時にいくつもの仕事している人。マルチタスクが得意。ジャンルが異なる焼酎とファッションの仕事を同時に進めていたり、複数の仕事を並行処理して、しかも人よりも短期間で仕上げてくる(笑)。
■焼酎スタイリストyukiko→「蔵元:宇都さん」のイメージとは?
(yukiko)「酒造り」という表現を通して、人として「ブランド」になれる可能性を秘めている人。堅実的なイメージもあるけれども、実は感性や言語表現が現代的で都会的。(たぶんご本人はそれほど気づいていないと思いますが……笑)その才能はまだ眠っている部分もあるので、より磨かれて”突出”していくことで「杜氏 宇都尋智」というブランドが出来上がる。スタイリストとしては、そういう“秘めている力”を存分に引き出してみたくなるんですよね(笑)。
[取材・撮影・文・構成] yukiko(ユキコ / 焼酎スタイリスト、ファッションスタイリスト)
[協力] 宇都酒造株式会社、色彩総合プロデュース「スタイル プロモーション」
※写真の無断転用、二次使用はお断り致しております。ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
現在それぞれ1,000人以上!メンバー登録FREEです
「焼酎&泡盛スタイル女子部」
「焼酎&泡盛スタイル男子部」
関連記事

焼酎スタイリスト®、ファッションスタイリスト。色彩総合プロデュース「スタイルプロモーション」代表。株式会社永谷園を経て“色が強み”のファッションスタイリストに転身。全国の蔵元らと連携して「焼酎スタイリスト®」として日本のお酒「國酒」を“流行×オシャレ”に発信。トレンドや美容情報に精通し、ファッション誌やビューティー誌にも登場。”時流”を掴んだお酒のコメントやアドバイスには定評がある。
蔵元や酒販店・飲食店からの信頼も厚く「蔵元公認 焼酎アンバサダー」「焼酎ナビゲーター」「泡盛スタイリスト®」「日本酒スタリスト®」なども務め、全国で講演やイベントプロデュース・企業研修を行う。大学の非常勤講師として教育分野でも活躍。(専門:販促色彩・ビジュアルプロモーション・ブランド構築・伝統文化産業)










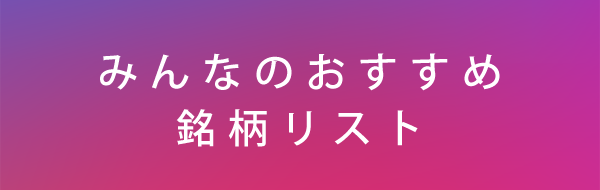


.jpg)